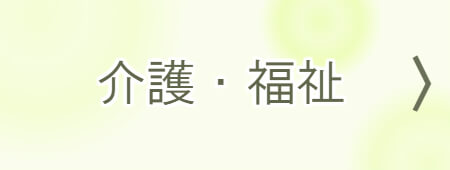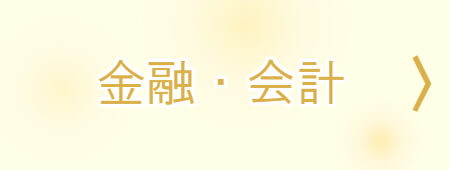ケアマネジャーの仕事内容
ケアマネジャーとは、介護を必要としている人を対象に個別の「ケアプラン」を作成するということが主な業務の仕事です。
現在の日本の介護福祉制度では、まず自立した生活を送ることが難しくなってしまった人に対し、その症状の度合いにより「要介護1~5」「要支援1~2」という段階を設定します。
認定を受けた度合いに応じて受けることができる介護保険の範囲が変わってきますので、それぞれ本人の様子を見ながら、どういった支援が適当であるかということを考える人が必要です。
ケアマネジャーとはそうした認定の申請とその後の介護保険を使ったサポートをまとめて提案をしていくことが仕事であり、全国の介護施設と自治体、さらに介護用品取扱店や地域共同体などと連携しながら業務を進めていきます。
なぜケアマネジャーという人が間に入る必要があるかというと、要介護認定は病気の重さと支援の必要性が必ずしも一致しないことが多くあるからです。
その象徴的なものが認知症ですが、認知症患者は身体の状態が比較的良好であるにも関わらず、徘徊などの問題行動を繰り返すということがしばしば見られます。
そのためコンピュータなどで一律に介護認定を決定してしまうと、実際の介護の必要と乖離した、意味のない支援をしていくことにもなりかねません。
そこで介護制度や介護の必要性について十分に理解をした「ケアマネジャー」により対面で様子を観察することで、本当に求められるケアプランを作成していくことができます。
ケアマネジャーの魅力、なり方、適性、必要なスキル
ケアマネージャーとして仕事をしていくためには、介護や福祉に関して詳細な知識を持っていなければならないことから、事前に資格を取得するのが通常です。
ケアマネージャー資格としては「介護支援専門員」というものがあります。
資格を取得するためには一定の実務経験が必要です。
具体的には、保険・医療・福祉分野で指定の受験該当資格を持ち、5年以上かつ900日以上の実務経験がある者と定められます。
なお指定の資格を取得していない場合も、10年以上かつ1800日以上の実務経験があれば同様に受験をすることが可能です。
試験は筆記試験方式で行われ、介護保険制度の内容についてかなり細かい部分までが出題されます。
かなり受験資格の設定が厳し目であるのに加え、筆記試験の合格率は15~20%程度と難易度も高く設定されています。
そのため実務経験があれば誰でもなれるというわけではなく、勤務をしながらコツコツと勉強をしていくことができる、努力型の人でないと取得は難しいでしょう。
そもそもケアマネジャーという仕事そのものに、粘り強い忍耐力が求められます。


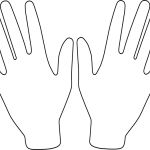



 動物と共に癒しを提供するアニマルセラピストの仕事とは?
動物と共に癒しを提供するアニマルセラピストの仕事とは? 要介護者の生活をお手伝い!介護福祉士になるには?
要介護者の生活をお手伝い!介護福祉士になるには?